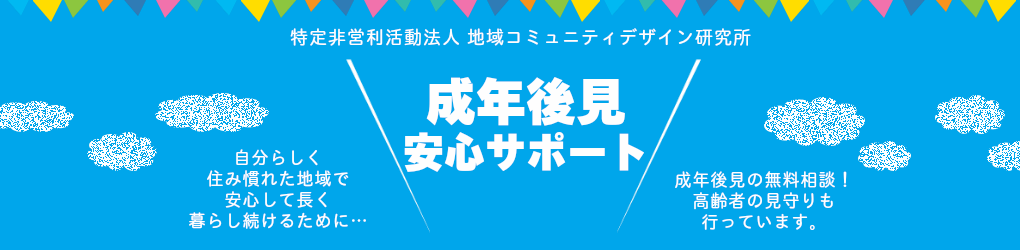代表理事
田中やすのり
私たち市民後見人が地域を変える!
 2000年に介護保険制度が始まり介護サービスが措置から契約へ移行したことを受けて、成年後見制度も両輪として施行されました。制度が始まった経緯を改めて鑑みると、成年後見制度が財産管理だけでなく身上監護も重視していることが分かります。
2000年に介護保険制度が始まり介護サービスが措置から契約へ移行したことを受けて、成年後見制度も両輪として施行されました。制度が始まった経緯を改めて鑑みると、成年後見制度が財産管理だけでなく身上監護も重視していることが分かります。
この身上監護に注力をしていくとなると、法律行為の専門家だけでなく、地域の介護や福祉サービスを熟知し、被後見人が望むサービスのベストミックスを考えていくことができる、地域に根ざした市民後見人が求められます。また、地域の福祉的なサービス資源とのネットワークを持ち、多様なサービス主体によるマンパワーを結集していくコーディネート力を有する市民後見人を育成し増やしていくことが急務です。
しかし現状を見ると、市民後見人への理解不足などにより、なかなか普及せず、育成も足踏みが続いています。そこで私たちはNPO法人を設立し、誰もが住み慣れた地域での暮らしを安心して続けることができるように地域社会全体でサポートしていくために市民後見人の活躍を創出していくことを目指しています。
また、社会貢献志向の高い市民後見人による後見活動は多くの付加的な地域貢献をもたらすものと信じています。例えば地域では自宅で病などに倒れて、誰にも気付かれることなくひっそりと息を引き取る「孤立死」が、社会に暗く大きな影を落としています。
一人暮らしの高齢者だけでなく、要介護高齢者や障がい者が、介護をしてくれていた同居の家族を亡くして生活の支えを失い、衰弱して命を落とすケースも相次いでいます。こうした悲しい事態が起きる背景として、孤立死に至った高齢者やその家族が、地域や社会とのつながりを完全に失っていたことが考えられます。地域コミュニティが希薄になっている都市型の街では、こうした悲劇的なケースがますます増加していく恐れがあります。市民後見人がこうした社会から孤立してしまった人の繋ぎ役となれる可能性は大いにあります。
さらには判断能力が不十分な認知症高齢者をターゲットとする悪徳商法が増えており、成年後見制度は悪徳商法への防衛としても必要性が高まっています。ここにも市民後見人の活用のメリットが大いに存在します。
私どもは「市民後見人」による誰もが安心して地域に住み続けることができる社会を再び創っていきたいと願っています。